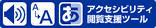松嶋ゼミ
松嶋秀明ゼミ(心理系)
(1)関心領域
思春期・青年期に生じる「不適応」(「非行」「不登校」「いじめ」など)と、その解消にむけた支援全般に興味があります。なかでも「問題」を、それを表出している当人に閉じたものとしてとらえるのではなく、家族成員や教師、カウンセラー、警察など,その当人をとりかこむ複数の大人の関係性の網の目(アレンジメント)のなかで生じるものとしてとらえたいと思っています。
これまでに更生保護施設、児童自立支援施設、小・中学校、放課後児童クラブや、いわゆる「子どもと若者の居場所」に関わり、フィールドワークやインタビューなど「質的研究法」をもちいて研究をおこなってきました。理論的にはナラティブ、社会構成主義、社会物質性アプローチ、ソーシャルセラピューティクスといった思潮に影響を受けています。
(2)研究指導の方針
大学生活のなかで締めくくりともいえるのが卒業研究です。どのような進路にすすむにせよ、卒業研究で自分の興味関心にむかってとりくむ体験は貴重だと思っています。そのため研究テーマは、個人の興味関心にしたがって自由に決めてもらっています。個々人の興味にそうのが一番だと思うからです。
研究をすすめるうえでは、(1)どのような問い(リサーチクエスチョン:RQ)をもつのか、(2)どれだけ収集したデータと対話し、なにが言えそうなのかを見極めていく作業が、重要な意味をもちます。RQは、学生のみなさんそれぞれが,これまでの生活経験からもつにいたった「個人的疑問」をもとに、これまで先人たちが蓄積してきた研究群と格闘しながら位置づけ、発展させていく作業です。
自分なりの疑問にこだわりつづけて、自分なりの回答を見出してもらいたいと思います。それぞれがもっている個人的な興味関心、疑問を大事にしつつも,自説に拘泥するのではなく、実際にえたデータと格闘しながら、自分のなかで新たな見方にたどりついてもらいたいと思っています。
以下に,過去10年間くらいの先輩方のとりくんだテーマの一部を載せておきます。
· 身近な人を「推し」と呼ぶ若者の心理~恋愛感情との違いに着目して~
· 褒めに対する肯定的でない反応はどのように生まれるのか
· 推し活における人間関係の変容
· 子どもの居場所への人々の想い
· 男性の化粧行為の形成過程
・被虐待経験からのレジリエンス ―成人期の女性のナラティヴから―
· 「熱狂的なファン」の自己アイデンティティ
· SNS上から対面への趣味のつながりの拡がりのプロセス
(3)研究上の相談、進学上の相談
大学院進学で松嶋研究室を志望される方は,事前にご相談ください。まず以下のメールアドレスからご連絡ください。 matsushima★shc.usp.ac.jp(★を@に変更してご使用ください)